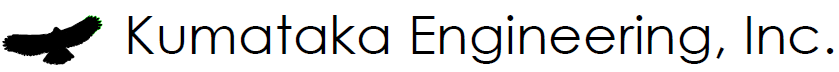問 題… 阪神高速の法円坂付近だけなぜ都市高速道路なのに高架ではなく街路と同じ地上を走っているでしょうか?
こたえ… 阪神高速道路の東大阪線はほぼ全線高架道路ですが、法円坂の辺りだけ地上に降りています。1978(昭和53)年に開通して以来、そのようになっています。実はこれには、やむにやまれない事情があって、この部分だけ平面道路になっているのです。
遺跡の真上を横切る高速道路
阪神高速東大阪線は1966(昭和41)年の都市計画で建設が決まりました。大阪市中央区法円坂から東大阪市の長田まで、中央大通りの上に高架で建設するという計画でした。
ところがその少し前、法円坂の一帯で難波宮の遺跡が発見されたのです。難波宮というと、古墳時代から飛鳥、奈良時代にあった宮殿で、当時はここが日本の首都でした。
歴史の時間に必ず習うあの「大化の改新」も、ここで行われています。そんなものすごく重要な、日本書紀にも書かれている史跡なのですが、その存在は時の流れの中で忘れ去られてしまい、戦前の頃にはもうその場所がどこなのかさえまったくわからない状態でした。1913(大正2)年、法円坂で奈良時代の瓦が発掘されていたのですが、当時はあまり重要なものとは思われず、また戦時中はその一帯を大日本帝国陸軍が接収していたので詳しい調査もできませんでした。
戦後、軍が撤収したあとに発掘調査をしてみて、この場所こそが幻の難波宮であるということがわかったのです。阪神高速東大阪線は、この難波宮遺跡の真上を通るルートでした。まったく、遺跡というものは本当に、どこから出るかわかりません。 特に近畿一円は古代遺跡の宝庫ですから。
高架道路を作る場合、基礎の杭を打ち込んだ上に橋脚を建設して道路を支えます。しかしここに杭を打ち込んでしまうと、まだ発掘されていない遺跡を破壊してしまうかもしれません。そこで、この区間は橋脚を建てなくていい平面道路にしたのです。
平面道路以外にも、この区間だけ橋脚をなくした長い吊り橋にする案もあったようですが、難波宮から北500メートルにある大阪城への見通し、景観が悪くなるということもあって、平面道路案を採択しました。それで結果的に建設費が安く済んだともいわれます。
また、前後の高架道路から平面道路へのスロープ部分の橋脚も、通常の間隔が30メートルのところを10メートルに詰めて、重さを分散させて基礎の杭が要らない構造になっています。

〈出典:まいどなニュース〉
いかがでしたか?
メルマガのバックナンバーをご覧になりたい方はこちら
ご意見・感想・お問い合わせもお待ちしております。
▶お問い合わせURL http://www.kumataka.co.jp/language/ja/contact/
いまや私たちの社会に欠かすことのできない道。
皆様の道づくり、社会づくりをクマタカはお手伝いします。
▶製品紹介URL http://www.kumataka.co.jp/language/ja/services/
▶ニュースリリースURL http://www.kumataka.co.jp/language/ja/news/
当社は、お客様へのサービス向上、広告、宣伝及び営業等の目的からCookieを使用しております。本メール内のURLよりWebサイトにアクセスすると、当社のWebサイト上におけるお客様の閲覧履歴と個人情報を紐付けて把握、分析する場合があります。